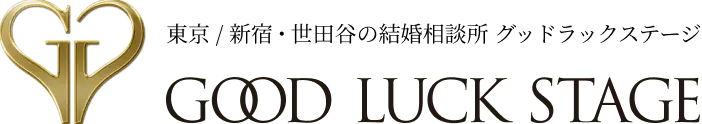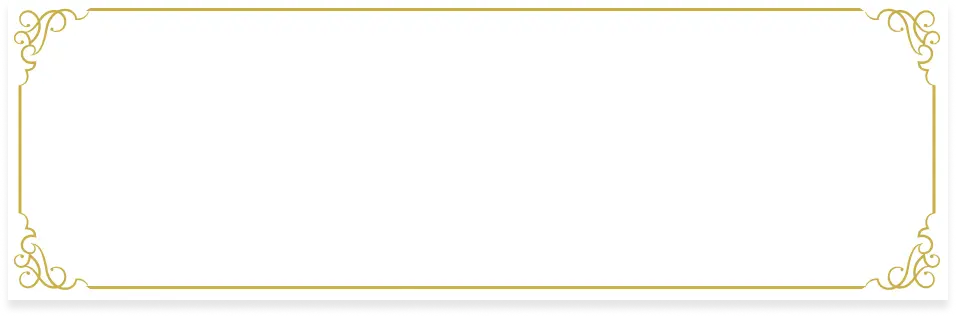婚活応援ブログ
Marriage Activity Support Blog
2025.08.04
なぜ「子供は早く欲しい」と「共働き希望」が女性に違和感を与えるのか?

婚活の場で「子供は早く欲しい」「共働き希望」という言葉は、決して珍しいものではありません。
男性がこの二つをセットで語ることは、人生設計の明確さを示す一面とも言えます。
しかし、多くの女性が感じるのは、表向きの理想と、実際の生活との間にある見えない“ズレ”です。
このズレは、単に「子供を持つこと」と「働くこと」の両立の難しさに留まらず、もっと根深い価値観の差異に根ざしています。
つまり、男性が軽視しがちな「妊娠・出産・育児のリアルな負担」と、女性の「その期間に大切にしたい生活感覚」がすれ違っているのです。
女性にとって、出産は身体的な大変さだけでなく、精神的な変化も伴う一大イベントです。
その時期に「すぐに働いてほしい」と言われることは、理想論ではなく、むしろ現実感の欠落として映ります。
また、共働きへの希望も、単に「二人で稼ごう」というだけでなく、「育児や家事の分担がどうなるか」が重要な判断基準になるのです。
本記事では、なぜ「子供は早く欲しい」と「共働き希望」が女性に違和感を与えるのか、具体的な理由と背景を女性目線で解き明かしていきます。
出産後すぐに働く前提に女性が抱く戸惑い
「子供は早く欲しい、でも共働きでやっていきたい」
このように言う男性に、女性はまず「いつから共働きを始めるつもりなのか?」という疑問を持ちます。
多くの女性にとって、出産後すぐに働くことは容易なことではありません。
産後の身体的な回復には個人差があり、自然分娩や帝王切開にかかわらず、最低でも数週間から数ヶ月の身体的な負担が続きます。
さらに授乳や夜泣きなど、睡眠が断続的に妨げられる育児環境は、精神的な疲労も相まって想像以上に厳しいものです。
それにもかかわらず、「共働き希望」とだけ語り、「出産後もすぐに仕事復帰を」という前提を当たり前のように口にする男性がいます。
こうした男性の発言は、女性に「自分の状況を理解していない」と受け取られやすく、不信感を生むことが少なくありません。
また、産後の生活が不安定な時期に、パートナーから「仕事もちゃんとやってほしい」と求められることは、女性にとって大きな心理的プレッシャーです。
「いつまでに復帰しなければならないのか」「子供の体調が悪い時はどうするのか」といった具体的な不安は、言葉にできないものの大きくのしかかります。
このため、出産直後の復職を当然視する態度は、女性の心に戸惑いと拒否反応を生みやすく、婚活関係における致命的な温度差を作り出します。
「小さいうちに一緒にいたい」気持ちを、まるで甘えのように扱われると心が離れる
女性の多くは、子どもが小さいうちはできるだけ一緒に過ごしたいという思いを抱いています。
この時期は、子どもが母親の愛情を必要とし、また母親にとっても子どもの成長を間近で見守る貴重な時間と認識されています。
しかし、「共働き希望」として男性側から語られるとき、この思いが「甘え」や「キャリア放棄」として軽視される場面が散見されます。
実際に婚活現場では、女性が「子どもが小さい間は育児に専念したい」と伝えた際、男性から「それじゃキャリアに響くよ」「今どき専業主婦は」といった返答が返ってくることが少なくありません。
女性にとって、この時期の「一緒にいたい」という願いは単なる感情的なものではなく、子どもの発達や愛着形成に関わる極めて重要なものです。
また、母体の回復や精神的な安定にも直結しているため、社会的な意義も伴っています。
こうした女性の願いを「甘え」や「贅沢」とみなす男性の姿勢は、女性からすれば「自分の人生観や価値観を否定されている」と映り、関係に深刻な亀裂をもたらします。
また、女性のキャリアを尊重することはもちろん重要ですが、それを理由に「育児期間のそばにいる時間」を否定するのは、女性にとって理解し難い行為です。
結婚生活においては、キャリアや家庭のバランスは人それぞれであり、尊重されるべき多様な選択肢の一つに過ぎません。
男性側がこの感情的な側面に寄り添わず、「共働き希望」だけを押しつける形で話を進めることは、女性の信頼を著しく損ねる要因となるのです。
“共働き希望”の中に、家事育児を自分ごととして考えていない男性が紛れている
婚活の現場で「共働き希望」という言葉は頻繁に耳にしますが、その実態は多種多様です。
中には家事や育児に積極的に関わる意思を示す男性もいますが、同時に「共働き」と言いながら、家事育児の大部分を女性に任せることを前提としているケースも少なくありません。
このような男性は口先では「家事も手伝います」「育児も協力します」と言うものの、具体的にどの程度関与するかは曖昧で、日常の家事や子育ての責任はあくまで妻の役割という認識が根強い場合が多いのです。
女性はそうした言動の奥に潜む意識のズレを敏感に察知します。
たとえば、保育園の送り迎えや食事の準備、子どもの体調不良時の対応といった日々の負担を誰が主に担うのか。
これが男性の口先の“共働き希望”と大きく乖離していると感じた瞬間、女性は大きな失望を覚えます。
実際、多くの共働き家庭においても、家事育児の負担は女性に偏る傾向があることが統計からも明らかです。
この現実を男性が理解せず、「共働き=二人とも働くこと」だけを意味すると考えている場合、
結婚後の生活設計として破綻のリスクが高いと女性は判断します。
特に、育休を男性自身が取得する意志がない場合、「共働き希望」は女性にとって“負担増の合図”となることが多いです。
育休を取ることで父親が積極的に育児に関わるという行動は、共働きを現実的なものにするための重要なステップですが、多くの男性はこれを避ける傾向にあります。
結果として、「共働きはするけれど、家事育児は妻中心」という前提が、婚活女性の心を遠ざけてしまうのです。
目先ばかりで将来的に子供が成人するまでを想定していない
婚活の現場では、「子供は早く欲しい」「共働き希望」と口にする男性が多くいますが、
彼らの多くは、目先の育児期間や短期的な生活の負担ばかりを見て、子供が成人するまでの長期的な人生設計や経済的責任を真剣に考えていないことが多いです。
育児は短期間のイベントではなく、成人まで続く長い道のりです。
教育費や進学、生活費など、経済的負担は大きく、精神的な支えも必要となります。
しかし、「共働き希望」という言葉の裏で、将来の負担や責任を深く想像していない男性に対し、女性は不信感を抱きます。
この目先ばかりの視点は、女性にとって「この人は家族の未来を真剣に考えていない」と映り、
婚活における大きなマイナスポイントとなります。
「いつから働くか」の認識のズレが決定的な破綻を生む
「共働き希望」自体は現代の婚活において特別なことではありません。
むしろ、子育てと仕事を両立させたいと考える女性は増えています。
問題は「いつから働くか」というタイミングの認識が、男性と女性で大きく異なることにあります。
多くの男性は、出産後数ヶ月から1年以内の復職を前提としており、
「育休は半年くらいで十分」「保育園に入ればすぐに働ける」といったイメージを持っています。
一方で女性は、子どもが幼稚園に入るまで、あるいは3歳になるまでは、できるだけ自分がそばにいたいと考える人が多いです。
これはキャリア放棄ではなく、母親としての責任感と子どもの成長に対する強い思いから来る自然な感情です。
この「いつから働くか」に対する価値観のズレが、婚活における決定的な破綻の引き金となります。
男性側が「半年で復帰できるよね?」と当然のように言い、女性側が「もう少し子どもと過ごす時間がほしい」と望むとき、双方の期待が大きく食い違い、「この人とは将来を共にできない」という結論に至るのです。
また、このタイミングの話が出る場面で、男性が女性の気持ちや生活実態に寄り添えず、
「共働きが理想だから」と一方的に希望を押し付ける態度を取ることもよく見られます。
女性は、共働きに対する理解だけでなく、
「自分の生活ペースや子育ての方針を尊重し、一緒に調整していける相手か」を見ています。
その視点を欠いたままの共働き希望は、結果として女性からの信頼を失い、婚活の失敗につながります。
人気の記事10選
2.交際終了のタイミングの判断の時期が結婚相談所では重要です
7.お見合いが終わってから駅まで一緒に帰る結果は良いか悪いか
10.お見合いのお茶代やデート代金のお支払いで分かる男性価値観
婚活の第一歩は直接相談!
婚活のことなら
世田谷・新宿の結婚相談所
グッドラックステージまで
お気軽にご相談ください
相談受付時間 / 11:00-19:00
定休日 / 毎週水曜日、年末年始休業12月30日(火)~1月4日(日)