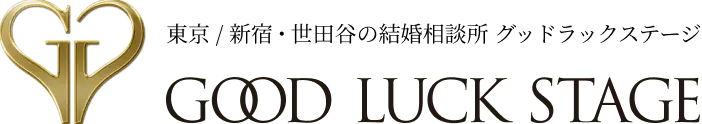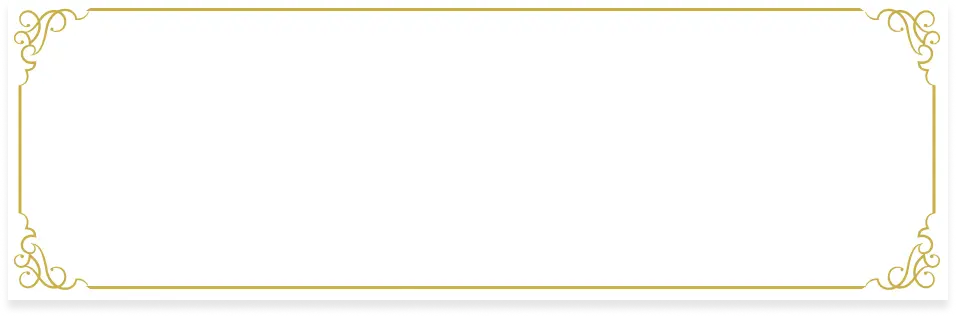婚活応援ブログ
Marriage Activity Support Blog
2025.08.05
将来設計の最初のテーマ“住む場所”成婚者はどう解決したのか

住む場所の話がまとまらずに、交際終了になるカップルは少なくない
交際中に直面する“最初の壁”――それが、結婚後にどこに住むかという「住む場所の話」だ。
お互いの職場・実家との距離・家賃相場・通勤時間など、複数の現実的な要素が絡むこのテーマは、話し合いがうまく進まないと、それだけで交際終了になってしまうケースも少なくない。
将来を見据えた関係であるからこそ、避けられないテーマでありながら、「自分の希望を伝えきれなかった」「相手が柔軟に聞いてくれなかった」――そんなすれ違いが破局の原因になってしまうこともある。
では逆に、住む場所の話がきちんとまとまり、実際に成婚していくカップルたちは、どのようにこの“現実的なテーマ”と向き合い、乗り越えていったのか。
本記事では、成婚者たちがどのように「住む場所」を決めていったのか――実例をもとに、具体的な選択とその背景をひも解いていく。
通勤も実家も考慮して“中間地点”で暮らすことにした
住む場所の話は、「どちらかが我慢する」「どちらかが譲る」という問題ではない。
実際に成婚した多くのカップルが選んでいたのが、「お互いの通勤や実家との距離を考慮して中間地点に住む」というごく現実的な選択肢だった。
これは感情の問題ではなく、純粋に生活効率の問題である。たとえば片方が東京西部、もう片方が千葉に実家や職場がある場合、埼玉・都内中央部など、双方に無理がない位置を自然に検討する。
一見すると“妥協”のように思えるかもしれないが、実際には「お互いにとって最もストレスが少ない選択肢を取った」というだけの話であり、理にかなった決断である。
また、こういった中間地点を選ぶ背景には、「お互いの実家を大切にしたい」という価値観が共通していることが多い。
どちらかが相手の実家近くに偏ることを避けたい、結婚後もバランスよく家族関係を築いていきたい――そんな想いが、自然とこの選択肢を後押ししている。
成婚者たちは、「お互いの生活動線を冷静に見て、地図上で一番自然な場所に引っ越しただけ」と語るが、そこに至るまでに感情を先に立てず、現実を優先できる関係性が構築されていたという点が、成婚に至った大きな理由だと言える。
リモートワーク中心の自分が、相手に合わせることにした
近年、特に増えているのが「リモートワーク中心の側が、住む場所の選定で柔軟に動いた」という事例である。
たとえば、週に1回しか出社しない職業に就いている人が、毎日通勤が必要な相手に合わせて、相手の職場の近くに住むことを選んだというケースが多い。
ここでは「どちらかが犠牲になった」わけではない。「通勤の負担が少ない方が動いた」という、極めてシンプルな判断軸が用いられている。
この判断は非常に論理的で、かつ長期的に見てストレスの少ない選択でもある。リモート中心の人にとっては、場所に縛られるメリットが少ない。
むしろ相手の働き方を尊重し、移動の負担を減らすことによって、二人の生活全体のパフォーマンスが上がる。
成婚者の中には、「相手に合わせた方が、結果的に自分の働き方も安定した」と感じている人も多く、こうした決断が無理のないものだったことが分かる。
さらに注目すべきは、この“柔軟性”の裏にある関係性である。
相手の状況や職業、日々の生活をきちんと理解し、尊重しているからこそできる選択であり、対等な関係性が築けていなければ成立しない。
つまり、住む場所をどちらかが合わせること自体よりも、「それが自然にできる関係だったかどうか」が、成婚できた理由そのものである。
職場が近い方が家賃を多めに出すことで、自然と決まった
通勤距離に明確な差がある場合、住むエリアはどうしても片方に寄ることになる。
このとき、成婚者たちがとったのは「家賃の分担でバランスを取る」という現実的なアプローチだった。
たとえば、片方が都心勤務・もう片方が在宅中心の場合、どうしても都心寄りのエリアに住むことになるが、家賃が高くなるのは避けられない。
その際に、「職場が近くなるほうが家賃を多めに出す」という形で、通勤と経済的負担を“交換”したのである。
これは、非常に理にかなった方法だ。片方が時間的・身体的に得をするなら、もう片方が経済的にフォローする。
こうした役割分担は、家事や育児といった将来のテーマにも通じる考え方である。
そして何よりも、この分担の話し合いが感情的にならず、冷静に進められていた点が重要だ。
「なんとなくの折半」ではなく、状況に応じた公平な分担を意識できている時点で、二人の間に現実を共有する土台がある証拠である。
住む場所の問題を「お金の話」として避けず、現実的に解決したからこそ、結婚後の生活でも同じように合理的に協力し合える関係を築けているのだ。
“この人となら仕事を変えてもいい”と思えたから迷わなかった
中には、勤務地の都合がどうしても合わず、「自分が仕事を変える」ことで住む場所を決めた成婚者もいる。
もちろん、簡単な決断ではない。しかし実際には、「この人と一緒に暮らしたい」という想いが先に立ち、迷わず仕事を手放した人も存在する。
重要なのは、この判断が“恋愛感情の勢い”ではないという点だ。
成婚者の多くは、「仕事を変える価値がある関係だった」と語る。
つまり、住む場所を選ぶうえでの基準は「損か得か」ではなく、「この相手との暮らしに、未来を感じるかどうか」である。
当然、キャリアや収入とのバランスは必要になるが、そうした条件をすべて受け入れてでも、「この人と住むことを優先したい」と思えたという感覚があったからこそ、行動に迷いがなかった。
そして実際にそうした選択をした人たちは、「住む場所の話をきっかけに、人生全体の価値観をすり合わせられた」と感じている。
自分の仕事を変えることを厭わない――それは、決して犠牲ではない。
“この人となら、生活も働き方も変えていける”と思えるかどうかが、住む場所を決める最終的な判断軸になっているのだ。
住む場所に正解はない。話し合いができるかがすべてだった
結局のところ、「どこに住むか」に正解はない。
どんなに条件を詰めても、完璧な立地、完璧な通勤距離、完璧な家賃バランスなど存在しない。
だからこそ、成婚したカップルに共通していたのは、「一緒に話し合える関係だったかどうか」それだけだった。
希望が完全に一致していたわけではない。むしろ、ズレているのが普通だった。
しかし、そのズレを「整理してすり合わせる」ことができたかどうかが、そのまま“成婚する関係かどうか”を分けていた。
「相手に言い出せない」「自分の希望を伝えられない」「反応が怖い」――
そう感じてしまう相手とは、どんなに条件が合っても、前に進まなかった。
逆に、「まず出してみよう」「一緒に考えよう」と思える相手とは、自然と話が前に進んでいった。
住む場所の話を避けず、対話を重ねた先に、納得感のある決断が生まれる。
このテーマに正解を求めるのではなく、「一緒に現実を整理できる関係」かどうかを試せたカップルだけが、成婚までたどり着いていたのである。
アクセス急上昇の記事10選
1.お見合いが終わってから駅まで一緒に帰る結果は良いか悪いか
4.デート中にお相手の距離感を知る方法は、一緒に歩く時の間隔
婚活の第一歩は直接相談!
婚活のことなら
世田谷・新宿の結婚相談所
グッドラックステージまで
お気軽にご相談ください
相談受付時間 / 11:00-19:00
定休日 / 毎週水曜日、年末年始休業12月30日(火)~1月4日(日)